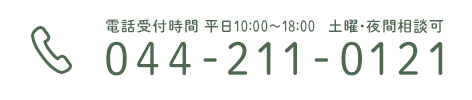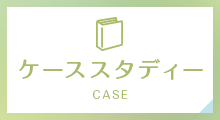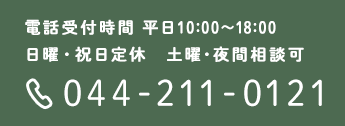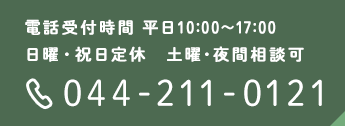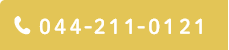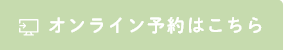Q 退職金未払 -会社が退職金を支払ってくれません。どのようにしたら良いでしょうか。
2020.01.16更新
A 退職金の請求が認められるためには、就業規則、労働協約、労働契約などの法的根拠が必要ですので、まずは、会社に退職金規程があるか確認してください。もし、退職金規程がない場合でも、慣行や労働者との個別の合意、会社と従業員代表との合意などにより、支給金額の算定が可能な程度に明確に定まっていれば、退職金請求権があるといえます。退職金が支払われない場合は、根拠となる就業規則等を示して請求しましょう。
懲戒解雇の場合には、退職金が不支給・減額となる場合もありますが、懲戒解雇の場合にも、退職金規程等に、不支給・減額の規程を明確に規定していなければ会社が勝手に不支給・減額にすることはできませんので、退職金規程を確認してください。
なお、退職金請求権の時効は5年間ですので、注意しましょう。
投稿者: