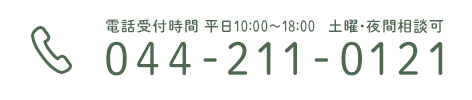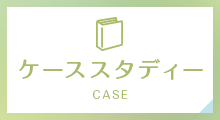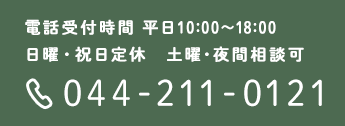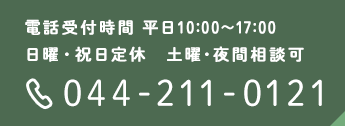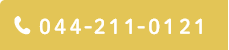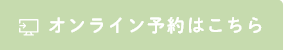中瀬奈都子弁護士については、こちらから。
離婚したい!となったときに、一番に頭に浮かぶのはお金の問題ではないでしょうか。
別居期間中の生活費、養育費、財産分与、年金分割、不貞行為やDVなどの慰謝料・・・後悔することがないよう、相手方としっかり話し合い、納得のいく合意を形成する必要があります。
ここでは、特にご相談の多い、別居期間中の生活費について取り上げます。
■「婚姻費用」という言葉をご存じですか?
婚姻費用とは、婚姻している夫婦と未成熟子をあわせた家族が、生活をいとなむうえで必要な生活費用のことです。具体的には、日常の生活費、医療費、教育費、保険料などのことです。
民法は、婚姻した夫婦には、扶養義務(民法752条)と婚姻費用の分担義務(民法760条)があると定めています。
婚姻費用は、多くは、別居をしたときに問題となります。
別居をしていても、離婚するまでは夫婦ですから、一方配偶者(義務者)が、他方配偶者(権利者)の婚姻費用を分担する義務があるのです。つまり、離婚するまで、収入が多い側が少ない側の生活費を分担することになります。
現実には、夫と比べて収入の少ない妻が、未成熟子をひきとって育てているケースが圧倒的に多いです。その場合、妻と比べて収入の多い夫は、妻の生活費と子どもの生活費(つまり養育費)を分担する義務があります。なお、離婚をすれば妻の生活費を分担する義務はなくなるので、子の養育費だけが問題になります。
【ポイント】
・別居しても、収入の多い方の配偶者は、少ない方の配偶者の生活費を分担しなければならない。
・離婚するまでは「婚姻費用」(収入が少ない方の配偶者+子の生活費)の問題、離婚してからは「養育費」の問題(※収入が少ない方が未成熟子を育てている場合)
☛「養育費」はいくらもらえるものなの?金額のほかに決めるべきことはあるの?…など「養育費」について気になる方はこちらへ!
■「婚姻費用」の金額はどう決めるの?
婚姻費用の金額をいくらにするかは、夫婦で自由に決められます。
しかし、夫婦間で話し合いがつかない場合には、家庭裁判所の手続きを利用することになり、その場合、婚姻費用は、裁判官が共同研究して作成した「養育費・婚姻費用算定表」をもとにして、計算することになります。
そのため、夫婦間で話し合う際にも、合意が形成できず、裁判所の手続きにうつることを想定して、算定表をもとにすることが実際多いです。
●「養育費・婚姻費用算定表」が2019年12月23日に改定されました!
2019年12月23日に新しい「養育費・婚姻費用算定表」が公表されました。
最新の統計資料に基づいて更新されたもので、従前の「算定表」よりも、一般的には増額されています!
★新しい「算定表」はこちら!
●新しい「算定表」を見てみましょう
「算定表」の見方は、まず子どもの人数と年齢に合った表を選び、義務者(支払う側の配偶者)の年収欄と権利者(支払われる側の配偶者)の年収欄が交差する点を確認します。そこに書いてある金額が、標準的な婚姻費用の額です。
なお、年収については、給与所得者の場合、源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額)を見ることになります。
例:会社員の夫 年収400万円 パートの妻 年収 75万円
子ども 6歳 別居後、妻が育てている場合
→まず、表11を見ます。
縦軸(義務者の年収/万円と記載されている軸)の左側の数字で「400」のところから右方向に線をのばします。横軸(権利者の年収/万円と記載されている軸)の下側の数字で「75」のところから上に線をのばします。この二つの線が交差する、「6~8万円」が、義務者が負担すべき婚姻費用の標準的な月額を示しています。
●「算定表」で解決できないケースも
「算定表」は、婚姻費用や養育費の簡易迅速な算定と保障を目指して作成されたもので、これによって、標準的なケースでの婚姻費用や養育費については、一目で基準額がわかるようになりました。標準的なケースとは、夫婦が別居し、夫婦の一方が子どもを育てており、子どもが学齢期であれば、公立学校に通っているというものです。
実際にはこの標準的ケースから外れる場合が多く見られます。たとえば、子どもが私立学校に通っている場合、別居後、権利者が住み続けている家のローンを義務者が支払い続けている場合などです。
その場合、「算定表」のベースとなっている「標準算定方式」にたちかえって、計算することになります。どのような事情が計算上、考慮されるのか、どのように考慮に入れるかは、過去の審判例等をふまえる必要があります。
例えば、私がこれまで扱った事件の中では、お子さんの保育園の費用や私立中学校の学費が、「算定表」上考慮されている公立学校の費用を大きく上回るケースが多々ありました。加算が認められるにはどのような事情・資料が必要か、どのように分担額を計算するかなど助言をし、いずれも、調停成立に至っています。
その他、家を出て行った夫が妻子の住んでいる住宅のローンを支払い続けているケースなども「算定表」に単純に当てはめただけでは算定できません。
ご自身のケースでは婚姻費用がどのように計算されるのか、是非、弁護士にご相談ください。
【ポイント】
・裁判所の手続きでは、裁判官が共同研究して作成した「養育費・婚姻費用算定表」をもとに、婚姻費用の金額が計算される。
・ただし、「算定表」は、「標準的なケース」を想定しているものなので、それぞれのご家庭の事情をふまえた金額の計算については、弁護士にぜひご相談を!
■婚姻費用分担の手続き
●調停・審判とは
夫婦間の話し合いで決まらなければ、「調停」を申し立て、「調停」が不成立だった場合には審判という流れになります。
「調停」とは、裁判官一人と民間人から選ばれた調停委員二人以上で構成される「調停委員会」が、当事者双方から事情を尋ねたり、意見を聴いたりして、双方が納得の上で問題を解決できるように、助言やあっせんを図る手続です。
婚姻費用分担調停では、「調停委員会」が、夫婦の資産、収入、支出などの事情を、当事者双方から聴いたり、資料を提出してもらうなどして事情を把握して、算定表をもとに、解決案を提示したり、必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。
「調停」は、あくまで、合意を目指す手続きですので、不成立になる可能性があります。不成立になった場合には、手続は「審判」に移ります。
「審判」は、裁判官が、当事者から提出された書類等種々の資料に基づいて判断を決定する手続で、婚姻費用分担審判の場合、双方の収入の資料などをもとに、裁判官が分担額を決定します。
なお、調停や審判で決まった場合、調停成立の場合は調停調書が、審判の場合は、作成されます。この調停調書や審判書は、相手が支払いを怠った場合に、給与や預金口座を差し押さえるなどの強制執行を行うことができる効力を持っています。
【手続きの流れ】
調停申し立て-(おおむね1ヶ月)
→ 第1回調停期日→(1ヶ月後)→第2回調停期日‥(以下、約1ヶ月毎に1回調停期日が行われる。)
→調停成立=調停調書作成
→調停不成立 ―(自動的に移行)→審判手続→審判=審判書作成
●重要なのは、申し立てのタイミング
ここで、一番重要なのは、調停の申し立てを行うタイミングです。
実務上、原則として、権利者が義務者に対して、婚姻費用を請求した時点から、婚姻費用の支払い義務があるとされています。そして、この「請求した時点」というのは、基本的には、婚姻費用分担調停または審判を申し立てた時点を指すとされています。
つまり、別居を開始して、1,2ヶ月話し合いを続けていたけれど、結局折り合わず、調停を申し立てたような場合、別居開始時点にさかのぼって支払わせることができないのです。
別居開始-(話し合い)―調停申し立て―――――離婚or別居解消
↑ ↑婚姻費用支払い義務↑
ここまでさかのぼれないので注意!
もちろん、調停で、別居開始時点までさかのぼって支払うという合意ができれば別です。しかし、実際にはそのような合意が形成できるケースはそう多くはありません。
調停となれば、裁判所に行くなどの手間がかかりますし、期日が約1ヶ月に1度の頻度であるため、一定期間かかってしまう一方、話し合いであれば、短期間に解決する可能性はあります。しかし、他方で、話し合いに漫然と時間をついやし、その期間の婚姻費用が結局支払われないというリスクもあるのです。
また、義務者である相手方が離婚を渋っている場合には、早く婚姻費用分担の調停申し立てをすることが得策になります。義務者にとっては、離婚に応じない期間が長くなるほど、その負担額が大きくなっていくからです。
このように、いつ調停申立てを行うか、その前に話し合いを行うかなど、相手方の性格や状況に応じて、戦略を立てる必要があります。
【ポイント】
・婚姻費用の支払い義務が発生するのは、基本的には調停(審判)申立て時点から
川崎合同法律事務所では、年間150人を超える方々から、離婚・男女トラブル・子どもに関するご相談をいただいております。たくさんの事例を経験しているからこそ、依頼者のみなさまそれぞれのご事情に応じた解決策を立てることができます。
女性弁護士が多数在籍していることも当事務所の大きな特徴です。
ご家庭の問題で悩みを抱えたときには、ぜひお気軽にご相談にいらしてください。
☛ 離婚・男女問題に関する案件のご依頼者様の声や解決までの流れなどは、こちら!
弁護士 中瀬奈都子